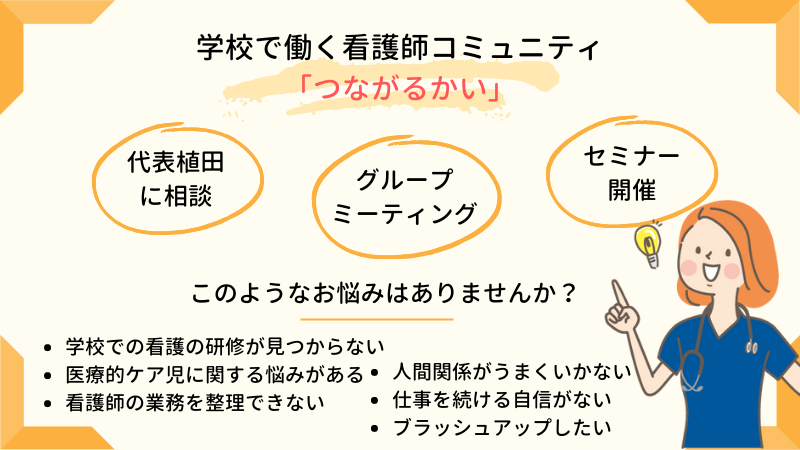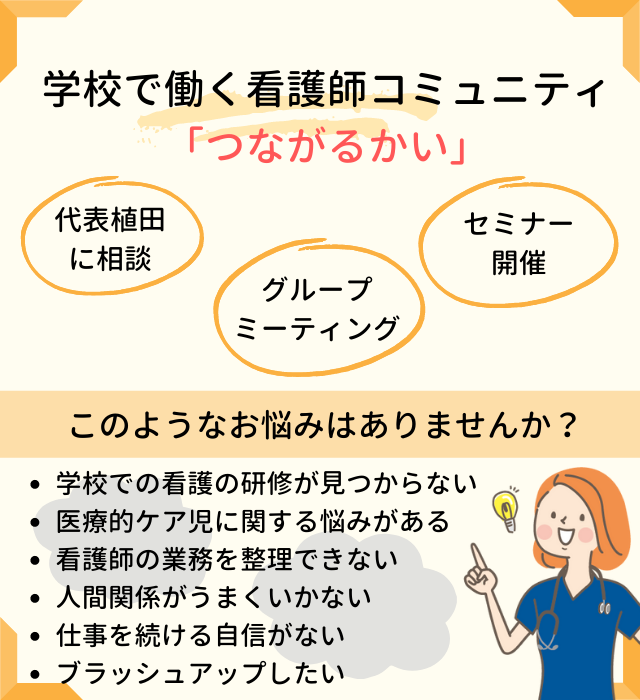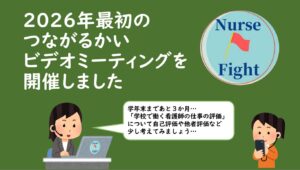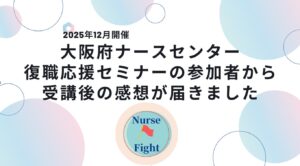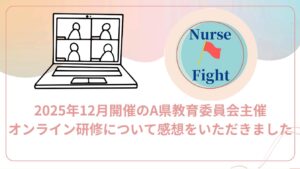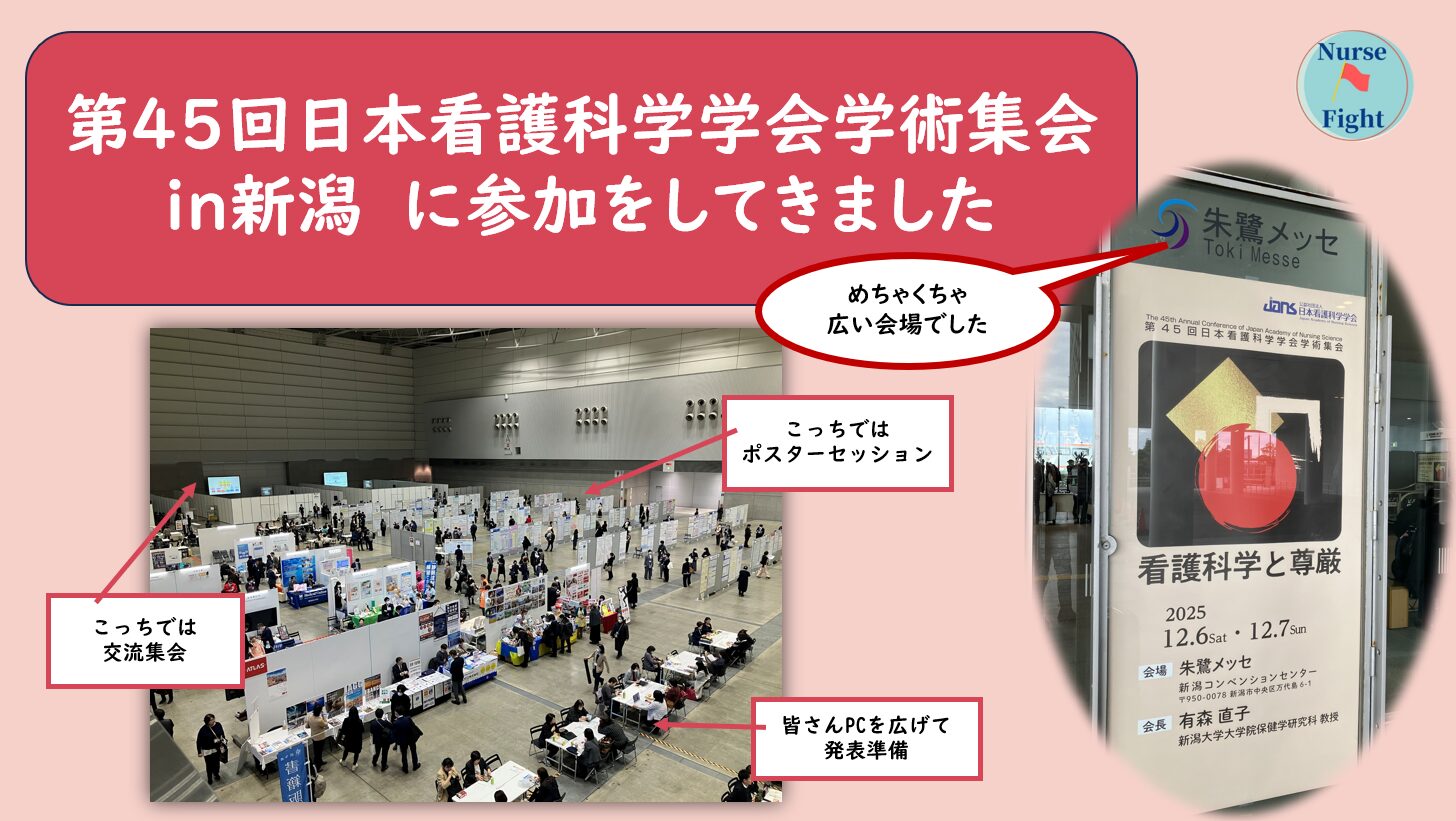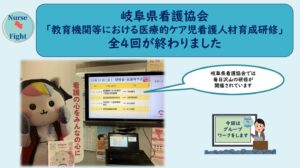昨年度につづいて今年度も学校法人大阪滋慶学園大阪医療看護専門学校の授業を担当させていただきます。
3年生が学ぶ「地域療養を支えるケアマネージメント」の科目の中で私は3回分の授業を担当し、子どもの学びを支える学校での看護について学生さんに説明します。
その1回目の授業を先日行いました。
学生さんは既に特別支援学校での見学実習は履修済みとの事だったので、実習で学んだ事も思い出していただきながら、1回目の授業では障害や病気がある子ども達の学校生活やそこに関わる看護師について動画も使いながら紹介しました。
まずは学生さんに質問
学生さんはそれぞれに異なる地域で小学校・中学校・高等学校の学校生活を送ってきていると思うので、授業を始める前にいくつか簡単な質問をさせていただきました。
皆さんタブレット端末を使って授業を受けているので、今回はGoogleフォームを使って私からの質問に無記名でその場で回答をしていただきました。
「医療的ケア」という言葉を聞いた事がありますか?という質問には9割の学生さんが「聞いた事がある」と回答してくださいました。
この回答は私は意外でした。
私の肌感覚ですが、例えば総合病院などで勤務する看護師に同じ質問をしたら医療的ケアという言葉を知っている看護師は9割もいるかな?と思います。
今の看護師養成課程では在宅看護を学ぶのが当たり前なので、若い世代には認知度が上がってきているのかな…と感じます。
また「保健室の先生とは別に看護師が働いている学校がある、という事を知っていますか?」という質問については、「知っている」が5割「知らない」が5割でした。
半数の学生さんは「やっぱり知らないよね…」とも思う一方で、半数の学生さんは「知ってくれている!」という方に私は正直ビックリしました。
この結果はもしかすると地域によって違いが出てくる可能性もあると想像しますが、私がこれから授業を担当させていただく学生さん達が半数でも既に学校の看護師の存在を知ってくれている、という事は嬉しい💕です。
成長していく子ども達の生活について知る
学生さんにとってはたぶん退屈な内容になってしまうとも思うのですが、ここはやはり言葉の意味や定義を確認しておく事は大事なので、こども家庭庁のホームページで公開されている資料を使いながら「医療的ケア」や「医療的ケア児」について説明しました。
具体的な「医療的ケア」の内容についても動画も使いながら説明をしました。
また、子どもは成人や高齢者とは異なり心と身体の成長の途中にあって、それは病気や障害がある子どもも同じである事、そしてその子の成長とともに生活の場が変化し看護師は様々な場面や場所で子ども達に関わっている、という事も紹介しました。
医療的ケアが必要な子どもが学校で学ぶ場面では、状況に応じて看護師が学校に配置され担任や養護教諭としっかりと連携する事で、担任はその子の教育的ニーズにあった授業を実践し、子どもは学びに集中する事ができる、という事もいくつかの事例を通してお話しをさせていただきました。
まとめ
病棟実習を控えた学生さん達にとっては、特別支援学校や小・中学校で看護師が果たしている役割を知るということは、正直、目の前の課題とはかけ離れたものだろうと思います。
まずは学生さんには医療機関での看護や医療をしっかりと学んでいただく事が大事です。
その上で、看護師はすでに医療機関だけでなく様々な場面や場所で必要とされているという事、そして、その中のひとつに学校での学びを支える看護があるという事を、学生さんのうちに知識として頭に入れておいていただく事は、卒後のそれぞれの仕事の中で、いつかどこかで使える知識になると思います。
あと2回の学生さんへの授業を通して、子ども達の成長発達を促す学校教育について、看護師が果たすべき役割や様々な職種との連携協働などに触れていこうと思っています。
学校法人大阪滋慶学園大阪医療看護専門学校👉https://www.ocmn.ac.jp/